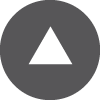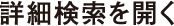読みもの
WEBでも教えて!青山せんせい <子どもの思春期は親の気づき次第! 後編>

りびえ~る本紙で掲載するたびに大きな反響がある、子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
子どもの思春期は親の気づき次第!<後編>
子どもの精神的な成長で、避けて通れないのが10代に訪れる“思春期”。
「何を言っても反抗してケンカが泥沼状態…」「どう接したらいいかますますわからない」…今まさに頭を悩ませている人もいるのでは(編集担当もしかりです!)。
でも、思春期は「親の気づき次第」。子ども自身の成長力を信じ、本当の自立を支えるために、親ができることってなんでしょうか?
後編では、思春期を通して子どもに身につくこととは何か、そのために大人はどう見守ればいいのか、具体的なヒントをお届けします! (前編はこちらから!)
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
思春期に身につくことって?
思春期のこの時期を通ることで彼らが身につけることがあります。
それは今後の人生を豊かに生きることになるのか、苦しく後を引くような生き方になるのかを左右するほど、大きく影響するものです。
というのも、私のところに相談に来る親・祖父母のほとんどが、この「思春期」を大きくこじらせてきているんです。社会人になって、親になって…その影響はずっとずっと響いているのです。
ではなぜそういうことが起きるのでしょうか?
答えは一つです。
この時期にヒトは、自分を模索するからです。
精神的に親から離れて、子どもとしての・自分としての在り方を探し始める時期。
そこで獲得していくことが、冒頭の「この時期に彼らが身に付けること」です。
この時期に親の言いなりで、自分で「自分」を考えてこられなかった子にどういうことが起きるかというと、その次の段階で非常に苦しむことが多い。
本来なら思春期に「自分とは」というアイデンティティを獲得し、それを土台として次の段階に進んでいくはずなんです。
しかしそれができていないと、次の段階になってから「思春期」のような自分探しが始まる。
一方で社会ではその年齢の彼らを「社会人」として扱うし、「大人」としての責任も求めます。
ですから、心が“こども”のまま自分探しを十分にできてこなかった子は、青年期に入ってから迷うことになるんです。
人間は、誰しもみんな迷います。
しかしこういう“こども”は、大きく心を病むかのように迷うのが特徴です。
大人にできること…子どもの「ろうそくの明かり」でいよう
もし、大人になったわが子に「たくましく、豊かに生きていてほしい」と少しでも願うのであれば、今、目の前の子どもがぐらぐらに迷っていたら、それを先回りして口出しするのではなく、
目を離さず(“監視”ではなく観察です)
口を出さず
いつでも応援してください。
いつでも弱音を吐ける、安心できる存在でいてください。
そして、子どものことなのに親がじたばたしてぐらついて、子どもに心配させるようなことはしないでください。
子どもが安心して、迷い、苦しんでさまよえるようにしてください。
ここでいう「迷いや苦しみ」は決して悪いものではないんです。
ただ、この人生においての暗がりのような場所はつらいものです。
そのつらさの道しるべになってあげてほしいと思います。
そのときに皆さんは、どんな道しるべになりますか??
煌々(こうこう)と灯るサーチライトのようにいますか??
灯台のような明かりになりますか??
街灯のように等間隔で明かりを灯しますか??
ぼんやりとろうそくのような明かりになりますか??
きっと真っ暗で 何も見えない苦しい中では、くっきりとした明かりは必要ないかもしれません。
等間隔のものは安心するでしょうが、それは過保護です。
できたらこの時期の子どもに必要な明かりは、消えそうで揺らぎはあるけれど決してなくならない、ぼんやりとしたろうそくのような明かりであってほしいと願います。
しっかりとくっきりと、大人が過干渉的に態度や言葉で示す必要はないのです。
私たちにできるのは、子どものことを見守り、考えて行動できるように支えてあげることなんです。
そう、優しいろうそくの明かりのように。
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数1.92万人(8月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。
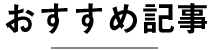
おすすめ記事