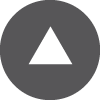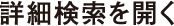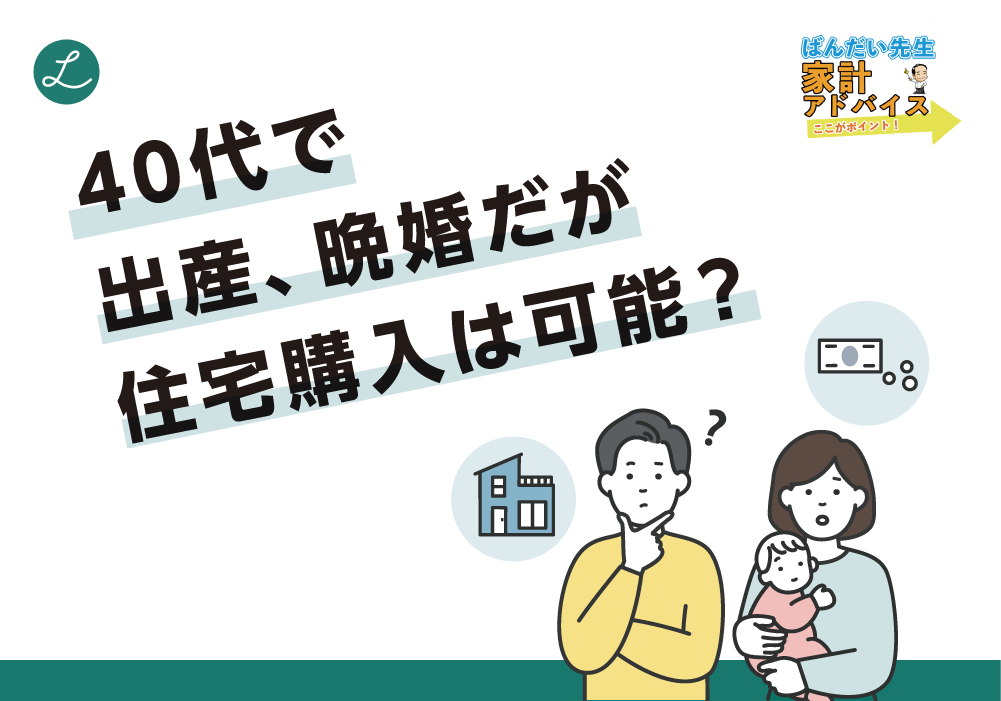読みもの
WEBでも教えて! 青山せんせい 原因は大人にも? 10代後半~若い世代の“無気力” 編

りびえーる本紙でも大きな反響をいただいている子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
原因は大人にも? 10代後半~若い世代の“無気力” 編
不登校や若い世代の生きづらさの理由・原因の一つとして、よく出てくるワードが「無気力」。
元気いっぱいだったはずの子どもたちが、なぜ無気力な状態になってしまうのでしょう?
今回は、子どもの無気力の正体とその原因、私たち大人への課題について考えます。
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
不登校の一因にも…青年期の無気力
普段は小・中・高校生のお子さんの親御さんからのお悩みに答えることが多いのですが、最近は18歳以上や20歳過ぎのお子さんの悩みへの相談が増えています。
せっかく受験しても学校に行けなくなった
突然親に決別宣言をしてきた
自傷行為による緊急搬送
就職してもすぐにやめてしまい引きこもりになってしまう
ヒトと関わりたくない
自分は結婚もしない、一人で生きていく宣言をされた
といった相談です。
よくよくお話を聞いてみると、とにかくお子さんに劣等感や自信のなさが目立ちます。
かろうじて通常の生活ができている子にも、「無気力」さを感じました。
無 気 力
最近よく聞くワードです。
不登校34万人…文科省が発表した主な原因は、この「無気力」だとしましました。
ある調査では、高校生の43.0%、大学生の49.0%が「何もしたくなくなる、無気力」な気持ちを経験したと報告されています。
「生きていることに意味を感じない、死を考える」とさえ感じているというのです。
これまで小中学生の相談やその実態からも、青年期の子どもたちの親からの相談はこのようになるだろうと予想はしていたものの、実際の相談の件数と内容に驚いているところです。
子どもの「無気力」を生み出しているのは…
若者が無気力になる主な原因には以下のようなものがあります。
1.過剰なストレス
仕事、人間関係、学業などによる過度なプレッシャーが、感情の不安定さや社会への恐れを引き起こし、無気力感につながります。
2.燃え尽き症候群(バーンアウト)
目標達成後や期待が報われないときに、精神的な疲弊から急激にやる気を失うことがあります。
3.無力感
自分の力では状況を改善できないという感覚が無気力を生み出します。
4.絶望感
将来に対する希望が持てず、現在の状況が続くと感じることで無気力になります。
5.無目標
明確な目標が持てないことで、やる気が湧かなくなります。
6.将来への不安
不確実な未来に対する不安が、目標設定を困難にし、無気力につながります。
7.孤独感
人との交流が制限されることで、孤独を感じ、無気力になる若者も増えています。
無気力な子どもたちは、言われたことはするけれど、指示されたことや必要と感じること以外はしないようになります。
無難なラインだけをこなし、自分の意志ややる気を見せることを避ける。
目立たず当たり障りなく、突出することなく、できるはずの能力を出さない。
できないわけではなく、避けているんです。
やる気がないのではなく、やる気を出し自分の意思を見せることを避けている。
それはなぜだろうと思いませんか?
この子たちは、生まれたときからこういう子だったかというとそうではないんですよ。
育つ過程で少しづつ、どんどん、こうなったのです。
やる気を見せたら「調子に乗るな」「でしゃばっている」。
チャレンジしたら「そうじゃない 余計なことをするな」。
失敗したら「だから言っただろう」。
意志を見せたら「大人の言うとおりにしなさい」。
人に迷惑をかけない 間違えない 失敗しない
人の眼を気にしろ 周りになんて思われてると思うんだ
そう言われ続けてきたら、そりゃあ何もできませんし、そんなマインドで育てられて、20年もしたら無気力になるのは当たり前です。
意志のないお人形のような子どもに育てておきながら、「さぁ自分で考えて行動しろ」とか「結果を出せ」なんて言われても出せるわけがない。
小・中学校時代、大人たちは子どもたちに、傷つかないように・失敗しないようにとお膳立てし、誘導しがちです。
まるでおままごとのような子育てをして、年齢だけ・体格だけ立派な大人に育てて、あぁよかった成人した…って、形だけの安心を手に入れて喜ぶ姿も見られます。
体の成長はしているのに、心と魂の成長はどこかはるか彼方に置いてきた子どもたちの姿が、「無気力」という言葉で片づけられているように見えます。
どこまで子どもを尊重しないのか…と私はつくづく思うのです。
変わるのは、おとな=親のほう
「子どもを変えたい」「今から間に合いますかね」と相談者に言われます。
そういうとき、「正直難しいね」と正直に伝えます。
なにが難しいかというと「親であるあなたがもう50年近くもそのままの考え方できていること」が難しいのです(辛口ですが…)。
子どもはなんとかなるけれど、親のあなたは半世紀近くその感覚で生きてきた。
変わることが難しいあなたがそばにいることで、子どもを苦しめてしまうことになりますよ…と伝えています。
子どもを変えようとするその考えを変えない限り、子どもは無気力のままだと思いますが、どうしますか?
私はこれが、8050問題・9060問題(※)の一部に通じているようにも思います。
今できることは、早い段階で親が変わることです。
子どもではなく、親の方です。
そこから先に、子どもへの関わりを考えましょう。
※80(90)代の親が50(60)代の子の生活を支える問題。親の経済的・身体的状態(介護)と、子どもの引きこもり・離職・障害などによる社会的孤立の長期化や子ども自身の高齢化などで、親子の共倒れが懸念される。
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4,000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数4.19万人(2025年1月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。
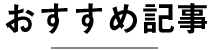
おすすめ記事