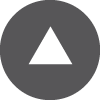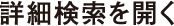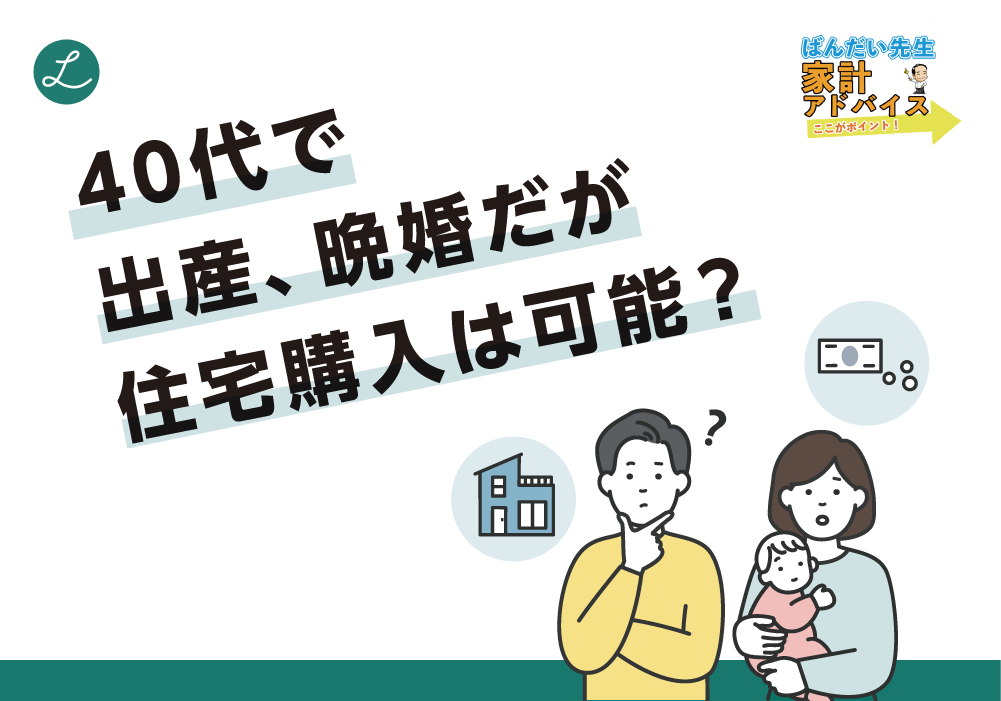読みもの
WEBでも教えて! 青山せんせい 親のタイプで考える! 子どもともっとうまくいくコツ<甘やかし・無関心型>編

りびえーる本紙でも大きな反響をいただいている子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
親のタイプで考える! 子どもともっとうまくいくコツ<甘やかし・無関心型>
心配でつい口出ししすぎる、思ったとおりに動かないとイライラする、子ども中心になりすぎる、子どもには必要以上に干渉したくない…あなたの子育てに当てはまるものはありますか?
心理学では、親の養育態度は大きく4つのタイプに分けられるのだそう。【1回目・<4つのタイプって?>はこちらから】
子どもの育ちにはお子さん自身の性質や周囲の環境も大きく影響するので、親のタイプだけで子育ての結果が決まるということではありませんが、自分の傾向を客観的につかむことが、よりよい子どもとの関わりにつながるのではないでしょうか。
過度に自分を責めるのではなく、客観視して改善できるようになりましょう…というのがこのタイプ分けの目的。
3回目は、甘やかし・無関心型に近い人への子育てのヒントについて考えていきます。
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
今回も、具体的にそれぞれのタイプについて掘り下げて考えていきます。
子育てを通して、子どもだけでなく自分の問題をも正しく認識する…これがこのタイプ分けの目的の一つだったりもします。
親の「4つのタイプ」…甘やかし型
甘やかし型の親は、子どもの顔色をうかがい、子どもの言いなりになるのが特徴です。
昨今の「叱らない・ほめる子育て」の弊害で子どもを叱れず、ほしいものをほしいだけ与えたり、好きなことを好きなだけさせたりし、我慢はよくない…という考え方です。
甘やかし型で育てられた子は、何でも自分の言う通りになると思い、自己中心的になりがち。
共感性に乏しく、他人の目線で物事を考えることが苦手です。
この特性だけを言うと、共感性に困難がある発達障がい・ASDなどが頭をよぎるかもしれません。
でも子どもの特性がどうであれ、親は辛抱強く「いい行動(本人が困らないための行動)」を教える必要があります。
このタイプの子どもは「あなたが一番」「なんでもOK」と甘やかされるので、思い通りにいかないと人を責めたり、自ら状況判断する必要なく育つため“空気の読み方”がわからず、周囲から浮きやすくなります。
幼いころは「子どもだから」「幼いから」で済んできたのですが、成長して周りの子どもの精神年齢が上がってくると、周囲と話が合わないことが多くなり、次第に孤立感を抱えてしまいます。
そのため、年齢でいうとおおむね小学3~5年生ごろ、周りとの関係構築が難しくなって、学校へ来たがらなくなることもあります。
子どもに対して年令相当の関わりをせず、過保護に育てた場合にもこの傾向がみられます。
前回お話したとおり、過保護に育った子どもは欲求不満耐性が低く他責傾向になります。
親が子どもから依存されることに存在意義を見出す場合、共依存となって抜け出しにくい点も共通しています。
親が先回りして問題解決にあたるのが「過保護型」、子どもの要求のままに何でもしてあげるのが「甘やかし型」ですが、よく考えてみると、これら両方の傾向を待っている人が多いかなと気が付きました。
ただ、私が甘やかし型の親によく言うのが「子どもの将来を考えていませんよね」ということ。
子どもをついつい甘やかしてしまう人や、もしかしてこれは甘やかしなのかなと考えるときは、「子どもの将来にとってよいことだろうか?」と考えてみてください。
子どもは“今”に集中しているので、先を見据えて考えて判断することができません。
この先どうなるかまでは考えが及ばないのは、まだそんな脳の段階にないからで、長期的スパンで考えることができる大人が、助言しながら一緒に考えることが必要なのです。
要求に応えなければ、その場では子どもが泣いたり怒ったりするかもしれませんが、我慢することも大事。
大人もそれができないと共倒れですよ。
また、甘やかされて育った子は、「自分の思考や感情は相手に伝わっている」という思い込みが強くなります。
これは認知バイアスの1つで、「透明性の錯覚」と言います。
この話は大人にも耳が痛いかもしれませんが、知るべきことなのでよく考えてみてください。
子どもや配偶者に対して「言わなくてもわかっているだろう」と思い込んでしまい、それゆえ「なぜ、わかってくれないのか?」とイラッとする…というのは多くの人が経験していることでしょう。
特に子育て中のお母さんが夫に対する不満を言うときのほとんどが、これに当たるのではないでしょうか。
「疲れているのをわかっているはずなのに、なぜ家事を手伝ってくれないのか?」
「こうしてほしいと思っているのに、なぜやってくれないのか?」
伝えてもいないのに、相手がわかっていると思い込んでいるのです。
逆に「言っても無駄、きっとダメだと言われる」という発想もこれに当たります。
誰もが陥ることのあるバイアスですが、「透明性の錯覚」が強いとコミュニケーションに支障が出ます。
子どもがこのバイアスに囚われないためには、きちんと言葉で伝えるよう促すこと。
同時に自分がまずそのバイアスにとらわれていないかも考えてみて。
大人になれていないオトナは、子どもの社会性を育めませんよ。
学校に行かないと社会性が育たない…などと心配する親御さんがいますが、先にすることは家庭内で社会性を育てることです。
親の「4つのタイプ」…無関心型
無関心型の親は、子どもへの関心が薄く、親自身の生活を中心に考えています。
衣食住を保証していれば親の責務を果たしていると考えていますが、根底に愛情が不足しています。
物理的には問題なく生活ができている、何不自由なく金品をあたえている場合もここに当てはまります。
子どもは愛情不足に陥ることで、被害感や疎外感が強く、自分を大切だと思えなくなり、お金や人間関係などでトラブルを抱えることがあります。
無関心型の親に育てられた子は、しつけをきちんと受けていなかったり、もしくはしつけだけは厳しくされている場合も多く、集団行動が苦手です。
コミュニケーション能力に乏しいがために対人トラブルを起こしたり、家庭の外に自分の居場所を求め、それが非行につながるケースも。
親が気が付いたときには子どもは親の愛情を拒絶していて、親に対し無関心になります。
無関心型の親は、「私たちはちゃんとしてやっているのに、子どもが勝手に悪いことをした」など、子どもの性格や価値観といった内面に問題があるか、能力が劣っているのが原因なのだと考え、決して自分に原因があるとは思っていません。
だから様々なところに相談に行きますが、そこでの主張は「子どもが悪い」「子どもの行動をどうにかしたい」というものです。
私が悪かったとは言うものの、原因は他に求めて親自身の問題に向き合っていないため、状況が変わらない。
こうなるとなかなか問題は解決しないことが多いものです。
昨今流行った「課題の分離」という発想もあります。
子どもに起きていることと自分の問題を切り離す、ということだけが独り歩きして、子どもが周りに迷惑をかけたり、問題行動をしても「子どもがやったことで私の問題ではなく、子どもの責任だ」という意識が強い場合です。
また、「うちは放任主義なので、子どもを自由にしています」というパターンもあります。
放任主義というやつですが、いやいやそれ「放置」でしょう!という場面に遭遇することも多くあります。
「放任」と「放置」、言葉は似ていますが、意味はまったく異なります。
「放任」には前提に信頼があり、子どもを信じて、子どもの自主性に任せる養育方針といえます。
放任主義の子育てをするためには、その前段階として安全に関わる事項や社会規範などをしっかり教えることが必要です。
社会生活を営むうえで最低限必要なルールが指導されていなければならないのです。
こうした基礎があって、子どもを信用して自主性に任せることは、とてもよいことです。
安心してさまざまなチャレンジをすることができ、子どもの成長を大きく促します。
一方の「放置」は、子どもに無関心でほったらかしていることです。
親としてするべき指導をせず自分のことに集中しており、社会のルール、常識、言葉遣い、マナーなどを教えないので、子どもは浮いてしまい、社会適応ができません。
「放任主義」「子どもの自主性に任せている」と言う人は、そのベースがちゃんとあるかどうかを振り返ることも大事です。
放任という言葉を親の忙しさの言い訳にしていないか、とも自問してみましょう。
さて皆さんは 4つのタイプのどれでしたか?
正直、どのタイプにも思い当たる部分があったかもしれません。
多くの人は自分の中に、これらの要素が少しづつまじりあっているものです。
それも十分に普通ですし、自分の傾向をとらえてバランスがとれるよう客観視し、意識していけるようになれば、きっといい変化が生まれるのではないでしょうか。
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4,000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数4.28万人(2025年5月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。
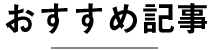
おすすめ記事