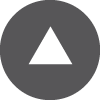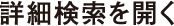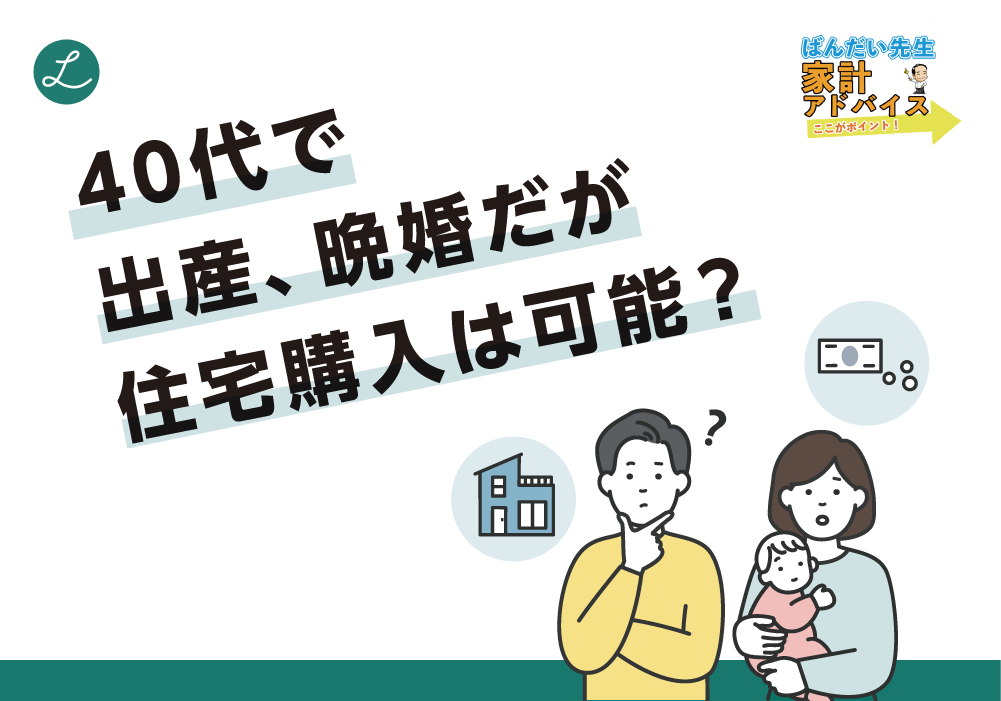

読みもの
WEBでも教えて!青山せんせい <「イヤイヤ期」は「やるやる期」ってどういうこと?編>

りびえ~る本紙で掲載するたびに大きな反響がある、子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版がスタートしました!
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんに繋がるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
「イヤイヤ期」は「やるやる期」ってどういうこと?編
2歳前後になった子どもに現れる、世に言う「イヤイヤ期」。
今までは親の言うまま、諭されるままだったのに、自我が芽生えて言うことを聞かなくなったり、何でも「自分で!」とやろうとしたり。親は振り回されることになり「魔の2歳児」などと称されることも。
でも、青山先生はこのころの子どもたちを「やるやる期」と称して、その後の人間形成に非常に重要な時期ととらえています。
自立の一歩を踏み出す大事な時期…親はどう接したらいいのでしょうか?
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
そもそも「イヤイヤ期」って何? それはなぜ「やるやる期」なの?
子どもの成長の過程で起こるもので、「自我の芽生え」の時期ともいわれますね。
初めて「自分」というものに気が付いて、「自分」を作り上げることがスタートします。感じて伝えたいコト、やりたいことをやってみたい…がたくさん芽生える、その際に、周りにうまく伝わらなくてイヤ、うまくできなくてイヤ…なのです。
「自我の芽生え・自立のスタート」は、すなわち「やる気にあふれる時期」。私はこれを「やるやる期」と捉えています。
なので、親は「イヤイヤが来た! うちの子、成長してる! ばんざい!」って思っていいところです(笑)
「イヤイヤ期」=「やるやる期」は、成長にどう影響していくの?
子どもたちはいずれ自立をしなければなりません。自分の人生を自分で切り開く力が必要になります。
その際に、自己選択をする場面が多く訪れますよね。 その自己選択の力は、小さなうちの「やる」「やらない」 「これをやってみたい」「やりたくない」 で練習をしていきます。
いきなり自己選択はできないものです。「イヤイヤ期」=「やるやる気」は、「この自己選択をする力」を育てる最初の練習なんです。
つまり、この時期のひとつひとつの「イヤ!」「やる!」は、子どもにとってはとても大きなこと。 でも、大人にとっては些細なことに見えてしまう。
コントロールして大人の都合のいいように言うことを聞かせるのは簡単ですが、長い目で見たときに、ここでしっかり練習できていることの意味はとても大きいことを理解してください。
では「やるやる期」のお子さんを持つ親たちはどんな風に見守り、どんな声かけをしてあげるといいでしょうか?
よくある場面が、「お風呂に入ってほしいときにイヤイヤする」とか、「公園や保育園から帰りたくない」などです。たいていは、「〇〇しないと××できないよ」…のような声かけをしがち。
しかし、これって脅迫のように聞こえませんか??
「〇〇しないと××できない」…これよりも、「〇〇すると××できるよ」「〇〇して××しようか」と言い換えてみてはどうでしょうか。
これはすべての世代の子どもたちへ、ひいては大人同士での声掛けにも通じるところ。
禁止や罰則でコントロールするのではなく、先の見通しを持つ練習の一環として、未来を見せるやり方で声をかけたほうがいいと思います。
その時に、「嫌なことを先にして後に楽しよう」という言い方はもってのほかです!
「先に宿題やったら後が楽じゃない」のように、先延ばしにしていること(=この場合は宿題)を、先回りして “楽しいこと”ではなく“不幸(イヤ)なこと”として位置づけるのはやめたほうがいいです。
これからやることはしんどいことなんだとわざわざ思わせる必要はないですよね!
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数1.76万人(6月現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。
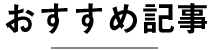
おすすめ記事