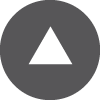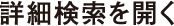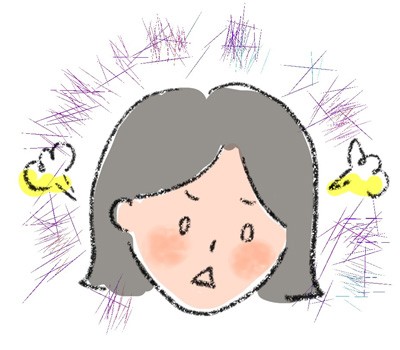読みもの
WEBでも教えて! 青山せんせい 親のタイプで考える! 子どもともっとうまくいくコツ<過保護・高圧型>編

りびえーる本紙でも大きな反響をいただいている子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
親のタイプで考える! 子どもともっとうまくいくコツ<過保護・高圧型>
心配でつい口出ししすぎる、思ったとおりに動かないとイライラする、子ども中心になりすぎる、子どもには必要以上に干渉したくない…あなたの子育てに当てはまるものはありますか?
心理学では、親の養育態度は大きく4つのタイプに分けられるのだそう。【1回目・<4つのタイプって?>はこちらから】
子どもの育ちにはお子さん自身の性質や周囲の環境も大きく影響するので、親のタイプだけで子育ての結果が決まるということではありませんが、自分の傾向を客観的につかむことが、よりよい子どもとの関わりにつながるのではないでしょうか。
過度に自分を責めるのではなく、客観視して改善できるようになりましょう…というのがこのタイプ分けの目的。
2回目は、過保護・高圧型に近い人への子育てのヒントについて考えていきます。
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
今回からは、具体的にそれぞれのタイプについて掘り下げて考えていきます。
子育てを通して、子どもだけでなく自分の問題をも正しく認識する…これがこのタイプ分けの目的の一つだったりもします。
親の「4つのタイプ」…過保護型
過保護型の親は、子ども本人が望む以上に世話を焼き、手助けをしてしまいます。
これを「過指示・過干渉・過保護」と呼んでいます。
子どもが失敗しないように先回りして安全を確保したり、障害を取り除いたりする結果、子どもは、本来なら発達の過程で身につく問題解決能力が身に付きません。
子どもを目の届くところに置いて、庇(ひ)護・保護のもとで育てたいという気持ちが沸き起こり、すべてを把握してどうにかしたいと願いますが、この行動が「支配」であり、監視に当たると親本人はわかっていません。
自覚していないので、子どもがすでに自分で判断できる年齢になっていても、親が余計な援助をし続けます。
子どもは依存的になり自立心が育ちにくくなるのですが、実は親が子どもに依存している結果として、子どもが依存的になっているといえます。
自立心が育たないのではなく、“自律”ができないために自立心の育ちを阻まれているんです。
「自分がやってあげないと」「この子は声をかけなければできない」そう思い込んでいたり、子どもから「やってほしい」と自分を求められることに価値を見出したり、やってあげることが親の役割だと思っている場合、共依存に陥りやすくなり、その関係性からなかなか抜け出ることができません。
そうすると、子どもは我慢する経験や失敗に対処する経験が少ないためストレスに弱くなり、失敗の原因を自分に求めることができず、他人や状況のせいにしがちになります。
こうなると、成長しても失敗を責められると意気消沈して何もできなくなるばかりか、責める側に攻撃心を抱いて人間関係をシャットダウンしてしまうこともあります。
手を貸すことをぐっとこらえるのは大変なものです。
私がサポートしている人たちも、最初はこれができなくて相当苦しんでいます。
「手を貸す」「やってあげる」「口を出す」「心配する」「子どもの失敗を見守る」これを実践するには、親自身の忍耐力が必要です。
そりゃあ、見守るよりも、「早くしなさい」「できたの?」「○○しなさい」と口出しして、手助けしてしまったほうがラクですよ。
しかしここもポイントで、親自身の欲求不満耐性が低いと、つい過保護になるのです。
欲求不満耐性とは、物事が自分の思い通りにいかないときに、その欲求不満の状態に耐えうる力のこと。ただ耐えるだけではなく、対処する方法を考えて対応していく力も含まれます。
耐性が低ければ、思い通りにいかないことに対してうまく対処できず、攻撃的になったり、逃避的な行動に出たりしやすくなり、それが非行・犯罪として現れることもあります。
この欲求不満耐性には、どう育てられたかが大きく影響します。
多くの人は子どものころ、ほしいものを買ってもらえずに我慢したり、学校や習い事などに行きたくなかったり、テストの点数が思いのほか悪くて親にどう見せるか困ったり……といった大小の困難に対して、それをどう乗り越えるか考えた経験があると思います。
これは実は大切なことです。
人生なんでも思い通りに行くわけがありません。とくに社会に出れば、さまざまな人と関わる中で譲歩したり、ときに我慢することも必要になります。
例えば「仕事の成果が出ない」「そもそもやりたい仕事ではない」と欲求不満状態になったとき、それをどう解決するか。
耐性が高ければ、「もう少し頑張って続けてみよう」とか「自分のやりたい仕事を見つけて、一から出直してみよう」などと健全な対処法を考えることができるでしょう。
子どものころから小さな我慢や、それに対処する経験をしてきたことで欲求不満耐性が高まっていきます。
欲求不満耐性が低い過保護型の親は、とにかく気が利く先回りの天才。
確かに困ることはないのですが、どちらかというと「自分がやりたくてたまらない」という衝動を抑えられない感じ。
ですから、この傾向を改善したいと思うのであれば、手助けしたい欲求を抑えて、それに対処しなければなりません。
これもトレーニングです。少しずつ我慢して見守ることを繰り返して、親自身の欲求不満耐性を高めていくことです。
また、このような人に共通する点として、過度に自罰的な人も多くいました。
子どもに何か困ったことがあると、助けてあげられなかった「自分のせいだ」と考えて、すぐに「私が悪い」というのです。
子どものために尽くし過ぎているにもかかわらず、常に罪悪感を感じたり、「自分でやりなさい」と言うことが愛情を感じさせない悪いことのような気がしていたり。
不要な罪悪感に支配されすぎて、問題を正しく認識できていない状態では、子どもにいい影響を及ぼすどころか、子どもに“何を・どこまで”したらいいのかわからなくなって混乱します。
ただ残念ながら、こういった親は多いものです。
親の「4つのタイプ」…高圧型
このタイプの人は、子どもに対してとにかく支配的で、親の言う通りにさせようとします。
何かと束縛し、ささいなことにも干渉。とにかくすべてにです。
従わない場合には罰を与えることも多く見られますが、その罰が子どもの執着を生んでいることにも気が付いていません。
この傾向が強い親は、勉強や成績・学歴など、社会的評価につながる部分に関して特に干渉が強くなることが多いです。
なぜかというと、“人の目”という世間体を気にするからです。
また、親自身が引け目に思っていることを子どもに重ねて、どうにかしようとします。
「迷惑をかけてはいけない」といいつつ、実は心の底では「○○だと私が恥ずかしい」「周り(義父母・自分の両親・先生・ママ友)がなんて言うか」と思っているからこそ、「周りの目をもっと気にしろ」「周りがなんて思っているか考えて」という考えに至ります。
そうなるともう、子どもは親や周りの顔色をうかがうのが常となり、自主的・積極的に物事に取り組もうとする意欲が育ちません。
言いなりになる方が簡単だからです。自分で考えても、それは否定されるから。
こういうタイプの親の子どもは、失敗したときに「そもそも自分の判断ではない」と他責思考で考えがちになるので、「自分は悪くない」「周りが悪い」という考えが育っていくことになり、結果として他罰的になることがあります。
自分の存在を認められていないという思いが強いため、自己肯定感が低いのも特徴です。
心の土台が作られていない状態ですね。
何より、お気づきの通り子ども自身が自主的に判断して動くことができないので、主体性が育まれにくくなります。
主体性が低ければ、社会でやっていくのは難しいと言わざるを得ませんね。
また、高圧的な子育てをすると、親の言う通りに物事を行わなかったときの罰をおそれて行動してしまうため、失敗を回避したいという気持ちが強くなります。
昨今「失敗したくない子どもたち」が増えているのは、ここにも要因を感じます。
私は不登校の支援もしているのですが、子どもたちが元気になっているにもかかわらず学校に復帰できなかったり、今一歩家から外へ・社会へ出ていけないのはこのタイプも多いのかなと思います。
つまり後遺症的にです。
ただ、もともと子どもたちは完璧主義だし、失敗したくないという気持ちが強いもの。
それを「失敗したらやり直せばいい」と思えるように育てていく必要があります。
しかし、親の完璧主義や理想を押し付けられ、高圧的にできなさを責められることが多いのが現状です。
親の要求が過度で期待が大きすぎるほど失敗する確率は高くなり、成功体験を積むことができません。
親の眼を気にすることから生まれる緊張や萎縮でうまくいかないにもかかわらず、結果だけを見て、「自分にはできない」「やっぱりうまくいかない」「自分はダメだ」と自己評価を下げていきます。
本当にもったいないですよね。
子どものやる気を高めたり、自己肯定感の元となる自己有用感を高めるには、外発的な動機付けより内発的な動機付けが重要です。
失敗したら罰を与えるのも、成功したら報酬を与えるのも外発的な動機付け。
「テストに合格したらほしいものを買ってあげる」というのもたまにはいいですが、継続するやる気は高まりません。
むしろそれが作為的だと嫌悪感を感じるようになると、もう従うことはなくなります。
特に思春期に差し掛かった子どもにはこの方法は向きません。
さらにこれを用いて、子どもが学校に行かなくなったり、逆に 親に威圧的な態度をとることもあります。
内発的動機付けである、本人の「やってみたい」という好奇心を引き出し「どうなっているんだろう」という探究心を育て、沸き起こるこうした知的欲求を満たしたいと思う気持ちや、自らを成長させたいと思う気持ちを育むことが、何より大事なのです。
次回は甘やかし型・無関心型について考えます。
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4,000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数4.25万人(2025年4月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。
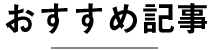
おすすめ記事